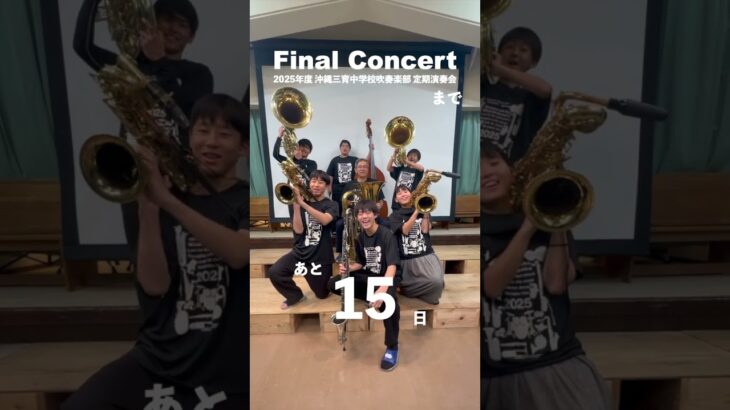沖縄で開催された合奏講習会の模様。A-B-Aの三部形式からなるこの曲の緩徐部には40分の練習時間を費やしました。ゆっくりのテンポの中では音楽の運びが遅いため、次のことが機能していないとその部分が悪く目立ってしまいます。
①全体の音量バランス(メロディが聴こえやすいか)
②音程(純正律を元に心地よいハーモニー感を)
③フレージング(フレーズの山を見つけよう)
①主旋律が聴きやすくあることは大前提ですが、副旋律や打楽器をどの程度活かすのか、バランスを緻密に考えることは必須です。メロディがメロディのハモリに移行しても気づかずに前の音量のまま突っ切ってしまうことは良くあることです。また、副旋律は時に主旋律を一時的に越えることがあっても、やはり文字通り副次的に扱うのが基本です。
②ゆっくりなテンポの音楽であるがゆえに、鳴っている一つの音の長さは長くなります。すると音程の悪さも当然のようにバレやすくなります。中学校などではまず緩徐部の音程を揃えるところから始め、テンポの速いところでも長めの音価の音を優先的に追究していくように段階的な過程を経ていくと効率化に繋がるかもしれません。
③単調な音楽は聴くに耐えません。正直眠くなる。なぜなら退屈だから。それをそう思わせないためには、一つ一つの音が持つ性格や色、和声進行における重力の推移を馬鹿にでも分かるくらいに明確に表現することが大切です。これこそがAIや打ち込みの音楽にはできない「人間だからこそできる音楽、そして芸術」ではないかと思います。
以上、3つの項目はゆっくりの時に目立つとはいうものの、速いテンポで疎かにして良いかといえば全くそんなことはありません。結局は常について回る演奏上の大切なポイントです。
また、このようなシーンの音楽作りに時間をかけすぎずに形にしていくためには、中学校や高校の吹奏楽部においては常にコラール練習をルーティーンとすることをお勧めします。
今回この催しを「後で知った」「参加したかった!」という声を多数いただいています。第二弾がいつか(ひょっとすると年内?)開催されますので、ぜひその時はご一緒ください!
楽曲: センチュリア/ジェームズ・スウェアリンジェン Centuria / James Swearingen
会場:豊見城中央公民館 中ホール
この合奏講習会は私にとって非常に大切な経験となりました。このような催しを全国各地で行うことが今の私の夢です。今回は中学生から大人の40人の方が集まってくださいました。もし皆さんのお住まいの地域でこのような会を開催できそうな場合、ぜひご一報ください。簡単な計画書をお送りし、ご相談をさせていただきたいです。ご協力者さまにはボランティアではなく、謝金やそれに代わるものをご用意する予定です。特に学校関係者や楽器店、吹奏楽指導者の皆さま、よろしくお願いいたします😊
ご質問やご要望などお気軽にコメントください。
チャンネル登録や「いいね!」も大変励みになります。ありがとうございます😊
【吹奏楽指揮&指導者 堀江龍太郎】
https://www.instagram.com/ryutaro.horie/
@maestro_brass
略歴:
指揮者、作編曲家、吹奏楽指導者。東京芸術大学附属高校、ライプツィヒ音楽大学、ベルリン芸術大学大学院首席卒業。ドイツ国家演奏家資格取得。ドイツ国立音楽学校専任講師、メニューイン音楽財団ソリスト、ノルトハウゼン歌劇場契約団員、東京佼成WOやゲヴァントハウス管弦楽団等、国内外の交響楽団で多数客演を務め、過去通算3,000回を超える演奏会に出演。北海道十勝しみず吹奏楽団音楽監督。客演指揮、学校指導、個人レッスンを国内外で行う。
吹奏楽指導経験:
全国の中学高校大学など70校以上を指導。台湾の吹奏楽団や高校の指導、中国や韓国では個人やグループレッスンも行う。遠隔地においてはオンラインを活用したレッスン、客演指揮やアンサンブルコンテストなどの作編曲も行う。ご質問やご要望などお気軽にコメントください。
![【センチュリア②】緩徐部合奏のコツ [吹奏楽合奏講習会in沖縄] 歌い方/和声/音型/バランス/サウンド](https://www.doga1.jp/brassband/wp-content/uploads/sites/2/2024/09/a92bd9cca60ba555bdf240a729f3ea5a-730x410.jpg)